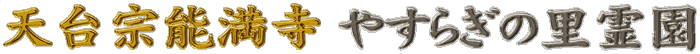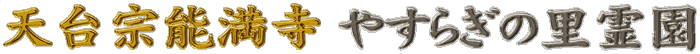|
身近な神 |
ついこの間まで、私たちのまわりにはたくさんの神様がいました。
夜が明るくなり、テレビが暮らしに入ってきたため、いつの間にか神様と縁遠くなっています。
日本は四季の自然に恵まれ、その恩恵を受けてきたため、特別自然を大切にし、
畏敬もしてきました。突然吹き出す風や荒れる山、わき出す水、木々にまで神を感じ、
恐れる謙虚さをもっていました。
人の心がすさみ、犯罪が横行し社会のモラルが低下している今、こうした神々に
思いを馳せるのもあながち無駄なことではないでしょうか…? |
 |
|
「山の神」 |
|
山の神はやきもち焼きでコワイものとされ、 |
|
奥さんをヤマノカミと言うのはここから来ています。 |
|
樹木や獣を支配する神で、山村では厚く信仰されています。 |
|
しかし農村での山の神は、春には田の神になって下りてくる |
|
稲作神です。秋にはお祭りをして山にお返しします。 |
|
神道の山の神は大山祇神(おおやまづみのかみ)などを |
|
祭っています。志摩半島や九州では、 |
|
山の神を「漁の神」として祭るところもあるそうです。 |
|
|
|
「風神」 |
|
突如として吹き荒れる風にも、昔の人は神を感じました。 |
|
風袋を背負った風神や、奈良・竜田大社に祭られている |
|
志那津彦命(しなつひこのみこと)、 |
|
志那津比売命(しなつひめのみこと)は有名です。 |
|
あの『古事記』『日本書紀』の時代から風神の記載があります。 |
|
悪い風を鎮めて豊作を祈る風神祭や風祭りはあちこちで行われ、 |
|
竹ざおの先に鎌を縛ってとりつけ、風神の風袋を |
|
切り裂いてしまおうとする「風切り鎌」の行事もあります。 |
|
 |
|
 |
|
「田の神」 |
|
田んぼの守り神。春、山から降りてきて稲の成長を見守り、 |
|
収穫が終わると山に帰るとされています。 |
|
農作業を始めるとき行う水口祭りや田植え始めのワサウエ・ |
|
サラビキ、本田植え後のシロミテ・サナブリ、 |
|
刈りあげ祭りなどはみな田の神のお祭り。 |
|
この神は「サ」で表され、サオリ、サノボリ、サナエ、サツキ、サミダレ、サオトメ、サクラなどは |
|
神にちなんだ名前だそうです。 |
|
|
|
「庚申」(こうしん) |
|
村の辻や道ばたに庚申塔が建っています。 |
|
庚申待ちの供養塔です。庚申は暦の十干十二支の一つの |
|
「庚申」(かのえさる)の日。この日はみんなでお堂に |
|
集まって、食べたり飲んだりしながら夜も眠らずに過ごし、 |
|
健康長寿を願います。中国道教の三尸(さんし)の虫の |
|
思想がもとになっています。 |
|
娯楽のない時代の楽しみの一つだったようです。 |
|
 |
|
 |
|
「案山子(かかし)神」 |
|
案山子も神です。今はいろいろの形のものがありますが、 |
|
やはり案山子といえば人の形をしたものを思い浮かべます。 |
|
もともと案山子には、田に注連(しめ)と神の依代(よりしろ) |
|
の人形やお札を立てるもの、また音や色、形で鳥や獣を |
|
驚かせるもの、最後に悪臭で鳥獣を追い払うものがあった |
|
そうです。このうち最後のものは「焼嗅(やいか)がし」の |
|
行事がもとになっています。「嗅がし」が「かかし」に転訛 |
|
最初の人形とくっついて現在の形になったそうです。 |
|
|
|
「馬頭観音」 |
|
農業がまだ機械化されていなかった頃、水田の耕作や荷物 |
|
の運搬など力仕事は馬に頼っていました。 |
|
農家は馬を大切にして住まいと一緒に厩(うまや)を造り、 |
|
寝起きをともにして家族同様の生活をしました。 |
|
今でも「馬力」は力の単位になっています。村はずれにある |
|
馬頭観音は、このような大事な馬の供養塔。 |
|
変化(へんげ)観音の一つです。 |
|
能満寺の参道にも馬頭観音の小さな供養塔があります。 |
|
 |
|
 |
|
「道祖神」(どうそじん) |
|
道祖神はもともと村の外からくる疫病や悪霊を村境で |
|
さえぎり、村を守ってくれる神です。だから別名を |
|
塞(さい)の神とかさえ(障・さい)の神と呼んでいます。 |
|
また「さい」は幸に通じ幸いをもたらすということから、 |
|
縁結びの神、旅人を守る神にもなっています。 |
|
1月14日、15日ころには道祖神祭りも行われます。 |
|
道祖神の形には丸石や文字を彫ったもの、 |
|
双神像などがあります。 |
|
|
|
「貧乏神」 |
|
みんなに嫌われる貧乏神も気の毒です。 |
|
押入れにいる小さく痩せた爺様とか、豆粒のような小男や、 |
|
杖をついた汚い爺さんの姿で表されています。怠け者の |
|
家を好み、住みつくと体がだんだん大きくなっていきます。 |
|
しかし、大事にもてなすと福運をもたらす神に転換すると |
|
いわれています。つまり貧乏神と福の神は一つの神の |
|
両側面だとも考えられています。もっと大事にしましょう。 |
|
 |
|
 |
|
「便所神」 |
|
正月やお盆にトイレに青しばをあげたり、年末に御幣 |
|
(ごへい)を供えたりするところがあります。隅に小さな |
|
神棚を作って女の人形を祭るところもありますが、 |
|
普通はご神体がなく棚だけの方が多いようです。便所神は |
|
厠(かわや)神、セッチン神、カンジョ神などとも呼ばれ、 |
|
あまり飾り立てる神ではないようです。便所神は |
|
お産の神になっています。トイレをいつも綺麗にしておけば |
|
美しい子が生まれるなどと言い伝えられています。 |
|
|
|
「井戸神」 |
|
各地に弘法大師の井戸とか姥(うば)が井、阿弥陀の井など |
|
の伝説が残っています。人の生活になくてはならない水を |
|
くみ出す井戸は、大昔から神聖視されてきました。かつては |
|
井戸にいつも塩を供え、簡単な神棚も作ってありました。 |
|
子供のお七夜に井戸神にお参りするところや、正月3日に |
|
つるべの縄をない、7月には幣束(へいそく)を立てて |
|
井戸の水替えをする地方もあるそうです。能満寺でも、 |
|
井戸の跡地に年末幣束を作りお飾りもあげます。 |
|
 |
|
|
|
|
イラストは kei さんです。 |
|
|